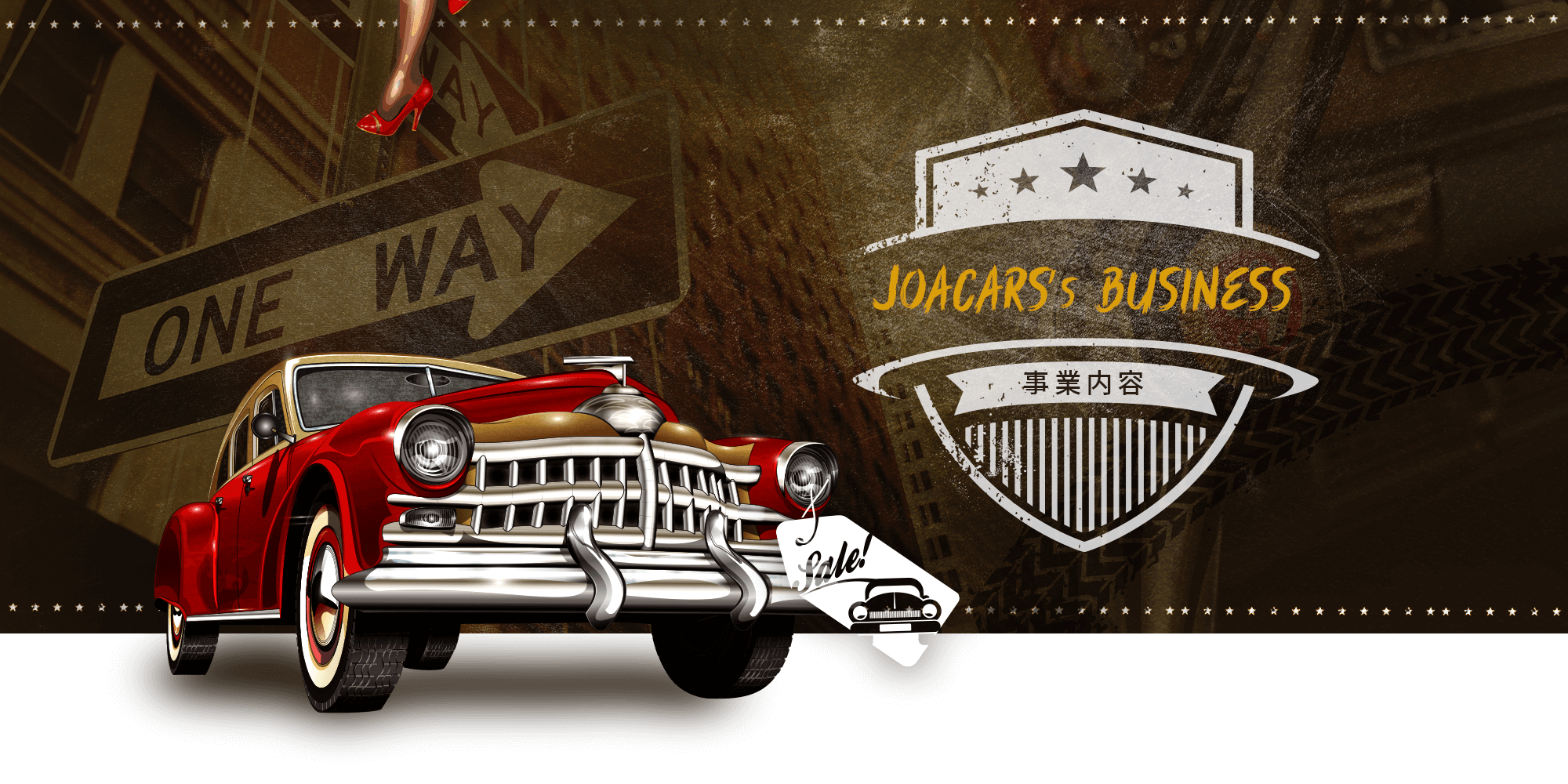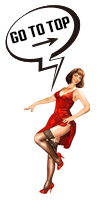月別アーカイブ: 2025年5月
リペアセッペのよもやま話~part15~
皆さんこんにちは!
リペアセッペの更新担当の中西です!
さて今回のよもやま話では
チェック項目
ということで、住宅補修工事者が施工後に行うべきチェックの重要性と、その具体的なポイントを深掘りしてご紹介します。
住宅補修工事では、工事が終わった瞬間が「ゴール」ではありません。むしろ、その後に行う施工後チェックこそが“本当の仕上げ”なのです。細部まで確認を行うことで、品質だけでなく、お客様の安心と信頼も完成します。
1. なぜ「施工後チェック」が重要なのか?
✅ クレームや手直しを未然に防げる
-
「色味が違う」「動きが悪い」「養生の跡が残っている」
→ 完了前に気づけばその場で修正可能
✅ お客様の“安心感”を生み出す
-
自らチェックを行い報告すれば、「しっかり見てくれている」と安心され、信頼につながる
✅ 品質の安定と職人の評価向上
-
毎回のチェックで施工の癖や弱点を自己管理できる
-
現場での対応力や仕上げの丁寧さが、次の依頼につながる
2. 施工後チェックの主な項目一覧
| チェック項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 補修箇所の仕上がり | 色・形・質感が周囲と違和感ないか | 光の当たり方でも印象が変わるため昼間の確認が理想 |
| 可動部の動作確認 | 扉・窓・引き出し・電動装置などの動き | 開閉に異音・引っかかりがないか |
| 清掃・養生撤去 | 養生テープ・ビスくず・粉塵などの残り | 「掃除しない業者」はリピートされにくい |
| 漏水・断熱・防音の確認 | 水回りや隙間補修の密閉度チェック | 水張り試験や手かざしで風漏れチェックを実施 |
| 製品保証・施工内容の説明 | 修繕内容を口頭または書面で説明 | お客様の「これで本当に大丈夫?」を防ぐ |
3. チェックを怠ったときのリスク
-
施工後すぐに不具合が発覚し再訪問に…
→ 信頼失墜+交通費+時間コスト -
清掃不足で「感じの悪い業者」という印象に
→ 口コミや紹介での評価に悪影響 -
「補修箇所は問題ないが他が気になる」と言われる
→ 認識のズレは丁寧な確認と説明で防げる
4. チェックは“お客様と一緒に”が理想
-
最終チェックはお客様と同行して確認する
→ 「この辺も見てほしい」といった追加ニーズが見える -
気になる点があれば即その場で修正提案
→ 「やり直し」ではなく「気づきの対応」で満足感アップ -
チェック報告書や写真報告を渡す
→ 書面があると後日のクレーム予防・信頼確保に有効
5. チェックは技術力の証明であり、サービスの完成
施工後のチェックは、単なるミス探しではありません。それは、
-
自分の仕事を最後まで責任を持って仕上げる姿勢
-
プロとして品質を担保する意思表示
-
次の現場、次の依頼を生む信頼構築の工程
なのです。
「確認しない職人」は、“完了しない工事”を残す
住宅補修工事において、施工後のチェックは工事を“完了”から“完成”へ導くための最終プロセスです。丁寧な確認を習慣づけることが、職人としての誇りであり、次の仕事への架け橋となります。
“直す技術”と“見届ける姿勢”の両方があってこそ、真に評価される補修職人となれるのです。
リペアセッペのよもやま話~part14~
皆さんこんにちは!
リペアセッペの更新担当の中西です!
さて今回のよもやま話では
ヒアリング
ということで、住宅補修工事において「ヒアリング」がなぜ重要なのか、どんなポイントに注意すべきか、実務で信頼される職人が行っているヒアリング術を深掘りして解説します。
住宅補修工事とは、住まいの不具合を「元通り」にするだけでなく、住む人の安心・快適・満足を取り戻すためのサービスです。そして、その出発点となるのが、お客様の要望を的確に聞き取る“ヒアリング”です。
1. 補修工事は「家の修理」ではなく「生活の修復」
例えば、壁のひび割れ、床のきしみ、水漏れなど——それは単なる構造上の劣化ではなく、お客様の生活ストレスそのものです。そのため、
-
「見た目も気になるけど、音や振動の方がつらい」
-
「子どもがいるので早く直してほしい」
-
「とりあえず最低限でいいが、将来の補修も考慮したい」
など、目に見えない希望や不安が多く含まれているのです。
この“気持ちの部分”を丁寧にすくい上げることが、補修工事の第一歩です。
2. なぜ住宅補修ではヒアリングが重要か?
✅ 1. 現状把握だけでなく「生活背景の理解」が必要
「同じ雨漏り」でも、住んでいる人の年齢、家族構成、使用頻度で最適な補修内容は変わる。
✅ 2. 不満・トラブルの種を未然に防ぐ
要望を聞き出せていないと、施工後に「色味が違う」「音が気になる」「もっと安くできたのに」といった不満が残る可能性が高い。
✅ 3. 顧客満足は「施工内容」よりも「対応満足」で決まる
実は、住宅補修工事では技術そのものより“話を聞いてくれた安心感”が評価に直結します。
3. ヒアリング時に確認すべき重要項目
| チェック項目 | 内容 | 理由 |
|---|---|---|
| 不具合の内容 | どこが・いつから・どうなっているか | 原因推定の初期情報 |
| 見た目と機能のどちらを重視するか | 美観 or 実用性 | 補修手法の選定 |
| ご予算の希望 | 希望額 or 上限 | 過不足ない提案のため |
| 生活スケジュール | 工事に立ち会える時間帯・日程 | 工事調整と近隣配慮のため |
| 使用頻度や重要度 | どのくらい使う場所か | 耐久性や仕上げ素材の選定 |
| 過去の施工履歴 | 以前誰かが直しているか? | 再発リスクや材料の互換性確認 |
4. 実践的ヒアリングのポイント
-
「どんなふうに困っていますか?」と生活目線で質問する
→ 技術的な言葉でなく、日常の悩みを引き出す -
「予算」「緊急性」「今後の使用頻度」の3点を軸に聞く
→ 優先順位を整理し、適切な提案へつなげる -
お客様が言葉にできない部分を「写真」や「ジェスチャー」で補完する
→ 非言語情報も大切なヒントになる -
ヒアリング内容をメモしてその場で読み返す
→ お客様と「内容の共有=認識の一致」ができる
5. ヒアリングは「信頼構築と再依頼」への第一歩
住宅補修工事の多くは、リピートや紹介で仕事がつながっていく業種です。ヒアリングの姿勢が丁寧であれば、「あの人にまた頼みたい」「知人にも勧められる」という信頼と紹介の連鎖が生まれます。
つまりヒアリングは、単に情報を聞く作業ではなく、次の仕事を呼び込む“信頼の投資”でもあるのです。
補修工事の技術は「聞くこと」から始まる
住宅補修の現場では、ただ技術があるだけでは選ばれません。お客様が安心して任せられる“聞く力”こそが、施工の精度と信頼を支えるカギです。
「話を聞く職人」こそ、地域に必要とされる“住まいのドクター”なのです。