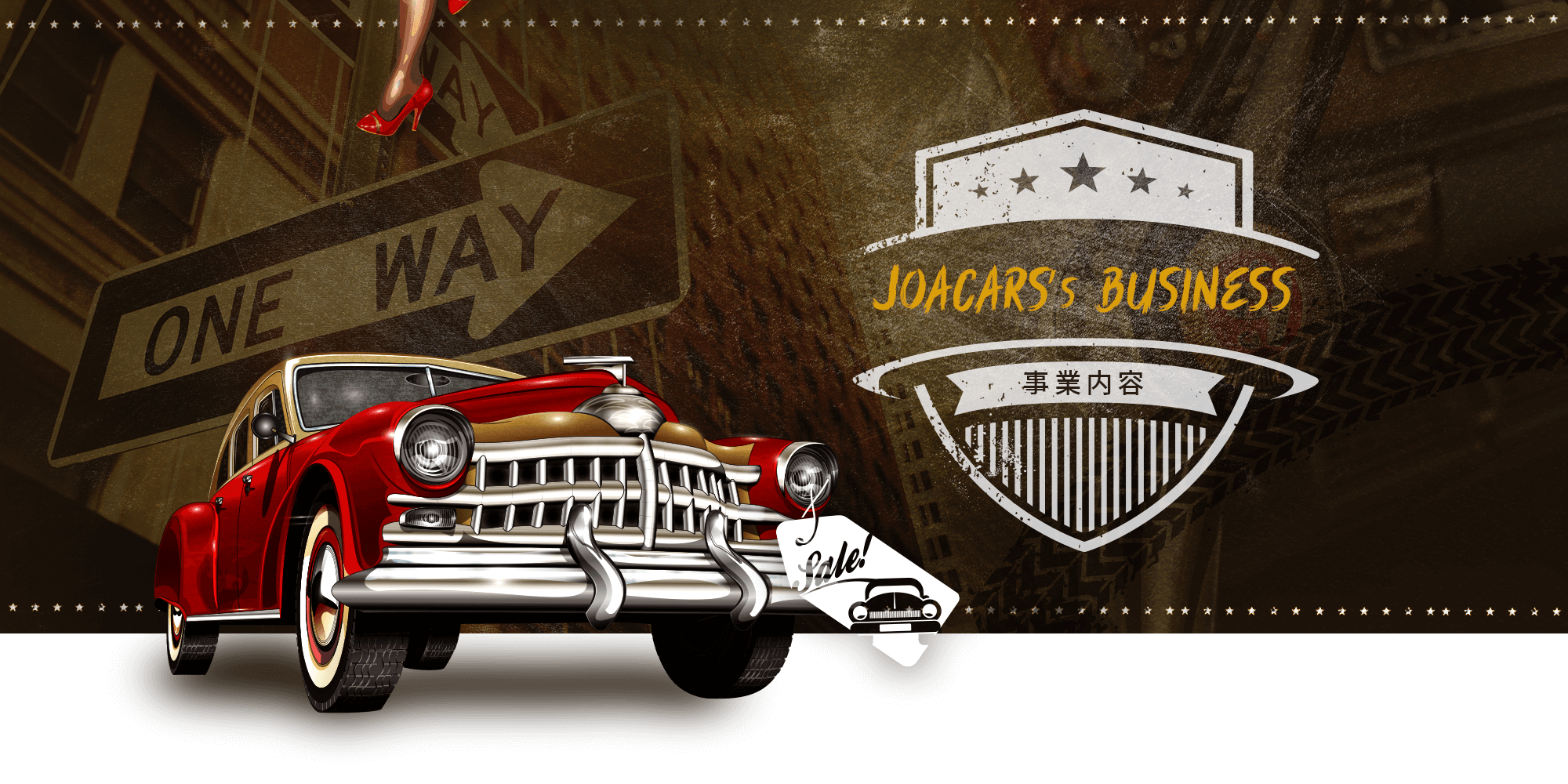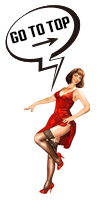日別アーカイブ: 2025年9月16日
リペアセッペのよもやま話~part22~
皆さんこんにちは!
リペアセッペの更新担当の中西です!
さて今回のよもやま話では
~変遷~
直すから“再設計する”へ。ストック時代の品質は現場でつくられる
新築中心の時代が終わり、建物・土木構造物・インフラの「長く使う」をどう実装するかが社会の主題になりました。補修工事は、ひびを埋める・錆を止めるといった対症療法から、劣化メカニズムを特定し、残存性能を評価し、将来リスクを管理する“外科と予防医療のあいだ”へ進化しています。本稿では、補修の世界でこの数十年に起きた変化を、素材・調査診断・工法・マネジメント・人材・環境の視点で整理します。
1|素材の変遷:モルタル一択から“機能材料の組み合わせ”へ
-
従来:セメント系モルタルやエポキシ樹脂で欠損部を埋め、塗装で保護するのが中心。
-
現在:目的に応じて材料を“処方”。
-
断面修復:ポリマーセメント、繊維補強モルタル、超高強度繊維補強コンクリート(UHPC)。
-
鉄筋腐食対策:防錆プライマー、再アルカリ化、電気防食(CP)、浸透型腐食抑制剤。
-
ひび割れ:低圧樹脂注入、結晶性浸透材、自己治癒促進材。
-
補強:CFRP/AFRPの連続繊維シート・プレート、鋼板接着、鋼繊維吹付。
-
仕上げ保護:可とう性の高い遮塩・遮水コーティング、光触媒・低汚染塗膜。
→ “何を塗るか”から**“劣化因子をどう遮断・拡散・制御するか”**へ。
-
2|調査診断の変遷:目視から“可視化+推定寿命”へ
-
昔:ハンマー打診・目視・簡易中性化試験。
-
いま:非破壊検査(NDT)を組み合わせて原因と範囲を定量化。
-
電磁レーダ(GPR):かぶり厚・配筋探査。
-
赤外線サーモ:浮き・剥離の面的検出。
-
反発度・超音波・衝撃弾性波:劣化度合い。
-
電位測定・コンクリート抵抗:腐食の進行可能性。
-
ドローン・点群(3Dスキャン):高所・大面積の迅速把握。
-
-
意思決定:現地データを劣化予測モデルに載せ、残存寿命・補修タイミングの最適化へ。
→ 「割れているから埋める」から、**“なぜ割れたか/次はどこが危ないか”**を先に押さえる運用に。
3|工法の変遷:部分手当から“機能の再構築”へ
-
表層更新(ライニング、可とう系塗膜):ひび追従・遮塩・防水で劣化因子の侵入を遅延。
-
断面修復:下地除去→防錆→再生モルタル→養生の標準化、仕上げで**含水・CO₂・Cl⁻**の入口管理。
-
補強・耐震:CFRP巻立て/鋼板接着/増し壁・ブレース/座屈拘束、部材単体からシステム剛性で評価。
-
プレハブ化:欠損部にプレキャスト部材を取り付ける置換型補修。工期短縮と品質の平準化。
-
ライフライン:更生管(SPR、CIPP)、マンホールのポリマーライニング。
→ 補修は延命だけでなく、**性能向上(耐震・耐久・維持費削減)**まで担う。
4|品質管理の変遷:職人技頼みから“数値+記録”へ
-
材料ロット・配合・可使時間の管理、環境条件(温湿度・風速)をデータ記録。
-
付着強度・引張試験・膜厚測定をロットごとに。
-
施工プロセスのDX:写真・検査表・センサーデータをクラウド台帳化し、引渡し=証拠の時代に。
→ 「ちゃんとやりました」ではなく、**“こういう条件で、こう施工し、こう検査して合格”**と語れる品質へ。
5|マネジメントの変遷:単発工事から“予防保全と資産経営”へ
-
点検義務・長寿命化計画の普及で、**計画的補修(予防保全)**が主流化。
-
発注も多様化:性能規定・包括契約・アライアンス方式で「結果」を共同管理。
-
在来→短工期:交通規制・操業・住民生活に配慮し、夜間・段階施工・無足場化(ロープアクセス等)を織り込む。
6|サステナビリティの変遷:壊して作り直すから“循環”へ
-
LCA/EPDで補修のCO₂削減効果を可視化(延命=最小環境負荷)。
-
選別解体・再資源化、防食や表層更新で更新周期を伸ばす。
-
低炭素材料(フライアッシュ、石灰系、ジオポリマー、再生骨材)の活用が増加。
→ 補修は環境投資でもある、という価値認識が定着。
7|人材・安全の変遷:技能+データの“二刀流”
-
資格とSOP:コア技能(はつり・注入・FRP施工)を動画SOPと実地評価で見える化。
-
高所・閉所・化学物質への安全対策を計画段階で織り込み。
-
現場教育:欠陥事例を因果で共有し、設計側へフィードバックの循環をつくる。
8|用途別の進化(ごく短く)
-
建築外装:タイル・PCaの浮き管理→部分置換/アンカー/軽量化、仕上げは低汚染で再塗装周期を延長。
-
橋梁・RC床版:塩害・疲労に対して表層置換+防食、床版増厚/FRP下面補強。
-
トンネル:覆工背面空洞の充填、ライニング更新、漏水の系統処理。
-
下水道:硫化水素腐食にポリマーライニング、管更生で掘削レス。
9|ケーススタディ(要点のみ)
A|海岸部RC桟橋の塩害
-
診断:電位測定・Cl⁻分析→腐食進行ゾーンを特定。
-
施工:断面修復+電気防食+表面含浸。
-
効果:腐食速度低下、点検周期を延伸。更新よりCO₂と費用を大幅削減。
B|集合住宅の外壁タイル
-
診断:打診+赤外線+引張試験。
-
施工:浮き部アンカー固定+部分置換、上から可とう形塗膜でクラック追従。
-
効果:落下リスク低減、再劣化を抑え再塗装周期を延長。
C|既存RC柱の耐震補強
-
診断:曲げせん断余裕が小。
-
施工:CFRPシート巻立て+定着ディテール最適化。
-
効果:靭性向上、居ながら工事で営業継続。
10|現場で使えるチェックリスト
計画前
-
劣化因子(中性化/塩害/凍害/疲労/ASR)の仮説立て
-
点検・NDTの組み合わせと採取位置計画
-
性能目標(残存寿命・耐荷力・水密・美観)の合意
設計・材料
-
付着設計(下地粗さ・プライマー相性)
-
補強のアンカー・定着・座屈検討
-
養生条件(温湿度・期間)、可使時間・膜厚の規定
施工・品質
-
除去範囲の境界明確化/粉じん・騒音対策
-
付着・圧縮・曲げ・膜厚・気密等の検査計画
-
写真・データ台帳(材料ロット/試験値/環境条件)
引渡し・維持
-
点検周期・補修保証の条件
-
劣化兆候の早期発見ポイント(錆汁・白華・鼓音・漏水跡)
-
予防保全カレンダー(清掃・小補修・再コート時期)
11|“いま”に合う実装:90日アクション
-
診断テンプレの整備:赤外線・GPR・電位・含水など、対象構造別の標準メニューをA3一枚で。
-
台帳DX:写真・検査値・ロットをQRで紐づけ、現場完了日にPDFを出せる体制に。
-
材料の引き出しを増やす:断面修復・防食・FRP・表面保護の4カテゴリ×各2製品を試験施工して、社内SOP化。
結び
補修工事は、壊れた箇所を塞ぐ作業ではありません。原因を解剖し、機能を再設計し、記録で未来に責任を持つ仕事です。
新築が減り、ストックが増えるほど、補修の価値は建物の価値=資産価値そのものになります。
次の現場では、診断の質→工法の必然→品質の言える化の三段跳びでいきましょう。
「直した」ではなく、**“なぜ・どう直し、どれだけ持つか”**が語れる現場から、安心とサステナが生まれます。